古代思想界の開花
春秋末から戦国時代にわたり、血縁を基盤とする「封建」体制が崩壊し、諸侯は新しい統一の原理を求め、富国強兵にともなう実力主義による積極的な人材登用を諸子百家行う中で、諸子百家と呼ばれる多くの思想家や学派が生まれた。
古代思想界の開花
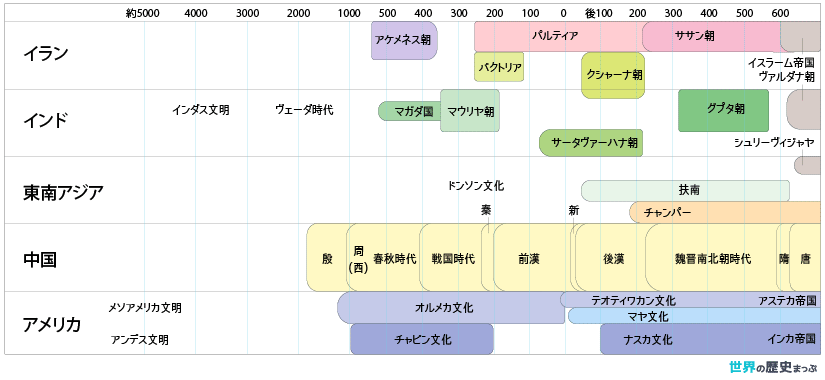
春秋末から戦国時代にわたり、血縁を基盤とする「封建」体制が崩壊し、諸侯は新しい統一の原理を求めていた。また、富国強兵にともなう実力主義による積極的な人材登用をおこなった。また、文字の使用は春秋期にはいると著しく拡大し、支配層だけに限られるものでなくなった。こういった文字の普及は、思想家の出現と無関係ではなかった。このような状況のもとに、諸子百家と呼ばれる多くの思想家や学派が生まれた。
諸子百家
| 諸子 | 孔子・老子・荘子・墨子・孟子・荀子 |
| 百家 | 陰陽家・儒家・墨家・法家・名家・道家・縦横家・雑家・農家・小説家・兵家 |
儒家
儒家は孔子(紀元前551頃〜紀元前479)の始めた学派で、家族倫理の実践によって人格を完成し、礼を実践することによって、ついには理想社会と天下泰平の実現が可能であるとした。
孔子は名は丘、字は仲尼といい、春秋時代の小国魯の曲阜(山東省)に生まれ、15歳で学問に志し、30歳ころ自身の思想を確立した。彼は、社会の基礎を礼におき、周(王朝)の礼を理想としたが、当時、礼が効力を失っていたので、それを立て直すために、人と人との間に自然に備わる道徳的な心情としての仁を強調し、この仁の完成により天下を平らかにすることができるとした。また、理想の政治は、天命を受けた有徳の天子がおこなうべきで、周の政治、とくに周公の治世を模範とした。これを徳治主義という。孔子は、古来の礼を回復し、政治と倫理・道徳を関連させる説をたてた。その言行は、『論語』に記録されている。儒家は後世、中国の正統の学問として大きな影響を与えることになる。
孔子の孫の子思の門人から儒教を学んだのが孟子(紀元前372頃〜紀元前289頃)で、紀元前4世紀ころ各地を遊説した。思想の中心に「仁・義」をおいたほか、天命が有徳者に移るとする改革論を説き、人間の本性は善であるとする性善説を主張した。儒教は魯からしだいに各地へ広がっていったが、最初に大きな影響を受けたのは魏である。儒家は、ここで多くの人材を養成して、魏に全盛時代をもたらした。
斉では全国から学者を招き、都臨淄に邸宅をつくり、ここに彼らを住まわせ保護した。
ここで孟子や荀子が活躍し、儒教を盛んにした。荀子(紀元前298頃〜紀元前235頃)は趙に生まれ、性悪説を唱え、本性が悪である人間から、悪をのぞくために礼による規律維持が必要であるとして、孟子とはことなる方向で孔子の思想を継承・発展させた。
墨家
このような儒教の発展に対しては、多くの批判者や対立する立場をとるものが現れた。孔子に対して、最初に異を唱えたのが墨家である。墨家の祖である墨子は、孔子の説く仁を差別的な愛とし、形式的な礼楽の説や家族道徳を第一とすることに反対し、血縁を超えた無差別平等の「兼愛」を主張した。万人に対する博愛主義にたち、浪費をいましめ、相互の助け合い(交利)を主張し、戦争は浪費の最大なものとして、非戦論(非攻)を唱えた。
道家
また、孔子の説く仁や礼を人為的なものだとして、一切の人為を排してあるがままの状態にさかわらず「無為自然」を説いた老子や荘子(紀元前4世紀頃)は、道家の祖となった。老子は、楚の人で姓は李、名は耳と言われるが、伝説的要素が多く明らかでない。孔子と同時代といわれるが、かなり後世の人とみられている。老子は、儒教が形式化し、それに合わせようとする不自然な努力を否定し、一切の人為的なものを排して、万物の根源を無であるとし、そして無の性格は自然であること、すなわち「無為自然」を主張し、すべての根源である「道」への合一を求めた(老荘思想)。この説は、のちに民間信仰と結びついて、中国思想界に大きな影響を与えた。
法家
法家の思想は、戦国時代に商鞅や韓非によって説かれた思想である。
この時代は富国強兵が普及し、国力の増強にあたっては、孔子の徳治主義は政治的に現実の実効性にそぐわなくなり、新しい強力な思想が求められた。韓非は戦国時代の韓の一族であるが、はじめ李斯とともに荀子に学び、韓に仕えたが用いられず、『韓非子』を著して政治の方法を論じた。すなわち、荀子の礼を実施するには法律的な強制をもってしなければならないとし、ここに法家の学が大成したのである。これを法治主義という。商鞅や韓非などに代表される法家の思想は、法によって民衆を統制し、国内を統一しようとするもので、秦はこの思想を採用し、法治主義は中国の思想史上重要な位置を占めることになった。
名家
また、戦国時代には弁者・策子などと称される論理学派があった。特定の学派の成立はなかったが、のち名家の名称が生まれた。名は事物に与えられた名称で、それは事物の本質やあり方に対応する。したがって名と実との間に不一致があってはならないとした。この派の代表的な思想家が公孫竜である。その説に有名な「白馬非馬論」がある。白馬は白と馬の2概念で、馬は1概念だから、白馬は馬ではないというものである。
兵家
このほか兵法を論じた兵家があり、戦国時代に兵法書が多く作られた。
戦術や戦略を研究して、一家をなした孫武・孫臏・呉起らの兵法学者が現れた。
縦横家
また、戦国時代の七雄が抗争する中で、外交戦略が展開された。各国は、あるときは合従し、あるときは連衡する同盟や外交術策を練った。この理論を唱えたのが縦横家で、代表的人物には蘇秦・張儀らがいる。
陰陽家、農家
さらに、天体の運行と人間生活との関係を説いた陰陽家(鄒衍)や、農業技術を説いた農家などの諸家があった。
『春秋』など儒教の経典をはじめとする諸子百家の文献に加えて、文学作品としては、黄河流域を中心とした各地の民謡を集めた『詩経』や、南の楚の屈原らの詩を集めた『楚辞』などがまとめられた。
『詩経』:中国最古の詩集305篇。戦国時代に儒家が編集したもの(孔子の編とされる)。五経のひとつである。『楚辞』:戦国の楚の屈原や宋玉らの辞賦を集めたもの。作品には南方系の方言がみられる。
古代思想界の開花が登場する作品
孫子兵法

孫正義やビル・ゲイツも愛読したビジネス戦略の礎となった古典、孫子兵法。諸葛亮孔明や曹操が戦略の根基とした無敵の兵法の誕生秘話をHDでドラマ化。
中国春秋時代の兵法書『孫子』を著したとされる思想家孫武の半生、紀元前500年頃の群雄割拠の時代を描いた物語。
恕の人 -孔子伝-

生涯をかけて仁・義・礼・智・信の心を説き続けた孔子は、後に儒教、道徳の始祖と呼ばれる。
しかし、孔子は完璧な聖人でもなければ、超人でもない。国を転々とし、ついに大業を成し遂げることなく人生を終えた不遇の人なのである。
大秦帝国 -QIN EMPIRE-

紀元前4世紀中頃。秦が弱小国から強国へと発展していく歴史を、「商鞅の変法」を中心に描く。楚、斉、燕など諸侯国に攻め立てられ滅亡寸前の秦の君主となった孝公は、魏国出身の稀代の策士・商鞅と共に法による一大改革に乗り出す。
大秦帝国 縦横 ~強国への道~

大秦帝国 -QIN EMPIRE- あらすじと登場人物の続きとなる作品。始皇帝が中国を統一する約100年前、“商鞅の改革”により国力増強に成功した秦を舞台に、縦横家が割拠した第26代君主・恵文王の時代を中心に描く。



