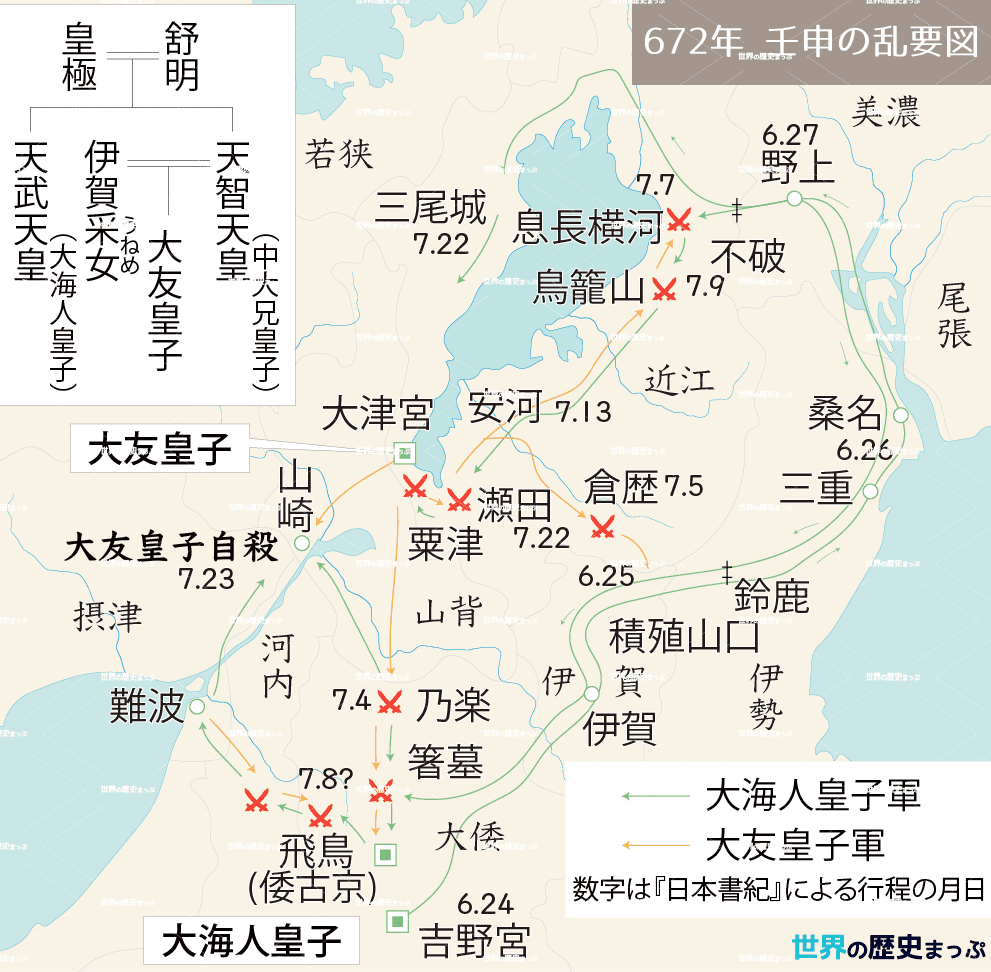律令国家への道
このページの使い方
- この「日本史まとめ」カテゴリのページは、単語を伏字を利用しています。●●●部分(伏字)をクリックすると単語が表示されます。再度クリックすると伏字に戻ります。
- その他重要な単語は赤字で表示しています。
律令国家への道
大化改新
1 大陸情勢(7世紀半ば〜)
2 国内の動き
- 蘇我氏の専横:●●●が厩戸王の子である●●●を殺害
- ●●●の変(645):●●●が、蘇我(倉山田)石川麻呂、●●●らの協力を得て、蘇我●●●・入鹿を滅ぼす
- 乙巳の変後、皇極天皇(中大兄皇子の母)から●●●天皇に譲位
- 中大兄皇子は皇太子に、左大臣に阿倍内麻呂、右大臣に●●●、●●●に中臣鎌足が就任
- 国博士に●●●と僧●●●を任命
- 国号を大化(最初の年号)とし、都を飛鳥から●●●に遷都
- 646年、「改新の詔」を発布
* (2)〜(7)などの一連の改革を「大化改新」という
3 改新の詔
『●●●』に記載はあるが、潤色が多く内容には検討の余地を残す
- 豪族の私有地・私有民を廃し、公地公民制をめざす
- 中央官制や、のちの「郡」にあたる地方行政組織●●●の整備
- 全国的な戸籍・田地調査 班田収授(法)の準備
- 課税台帳の計帳を作成し、統一税制の施行をめざす
史料チェック: 改新の詔
其の一に曰く、「昔在の天皇等の立てたまへる子代の民、処々の●●●、及び、別には臣・連・伴造・国造・村首の所有る●●●の民、処々の●●●を罷めよ。仍りて食封を大夫より以上に賜ふこと、各差あらむ。」
其の二に曰く、「初めて京師を修め、畿内・国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬を置き、及び鈴契を造り、山河を定めよ。」
其の三曰く、「初めて戸籍・●●●・班田収授の法を造れ。凡そ五十戸を里と為し、里毎に長一人を置け。」
其の四に曰く、「旧の賦役を罷めて、田の調を行へ」(『日本書紀』)
4 その後の動向(乙巳の変後〜649年)
王権や中大兄皇子の権力が拡大し、古人大兄王(中大兄の異母兄弟)、蘇我倉山田石川麻呂らあいつぎ滅ぶ