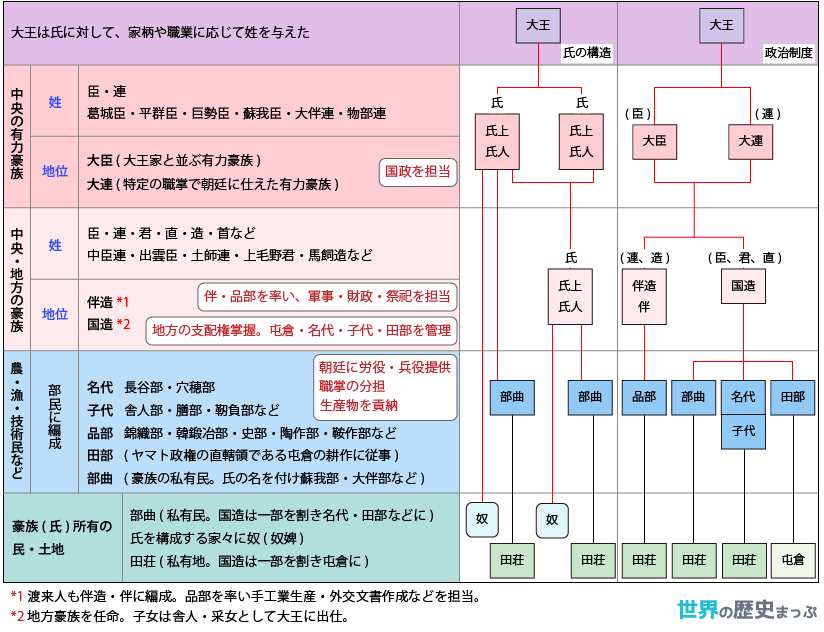古墳とヤマト政権
このページの使い方
- この「日本史まとめ」カテゴリのページは、単語を伏字を利用しています。●●●部分(伏字)をクリックすると単語が表示されます。再度クリックすると伏字に戻ります。
- その他重要な単語は赤字で表示しています。
古墳とヤマト政権
古墳時代のひとびとの生活
1 豪族と民衆の分離
- 豪族:集落から離れた場所に環濠や柵列のある居館を造営、倉庫群が付設
- 民衆:
- 複数の竪穴住居と平地住居、高床倉庫など
- 竪穴住居内には作りつけのカマドを設置(*炉と区別)
2 生活・風習
- 土器:弥生土器の系譜を引く赤褐色で素焼きの●●●に加え、朝鮮半島から新しく伝わった硬質で灰色の●●●を製作
- 衣服:上下分離(男性は衣とズボン風の袴、女性は衣とスカート風の裳)
- 農耕儀礼:豊作を祈る春の●●●、収穫を感謝する秋の●●●など
- 祭祀対象:
- 整った形状の山、絶海の孤島、巨岩、巨木など
- 三輪山を神体とする●●●神社
- 沖ノ島を祀る福岡県宗像大社の沖津宮など
- 呪術的風習:鹿の骨を焼き吉凶を占う●●●、熱湯に入れた手がただれるかどうかで真偽を判断する●●●、穢れを払い災いを免れる禊・祓など