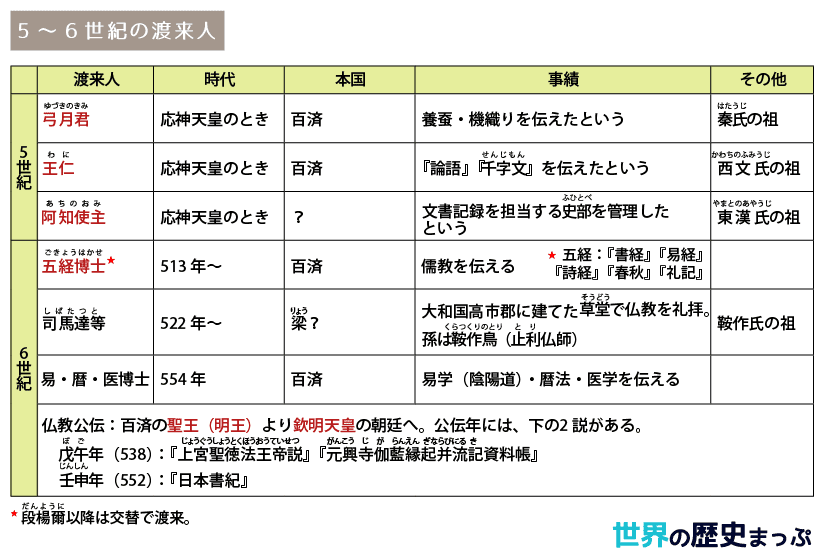古墳とヤマト政権
このページの使い方
- この「日本史まとめ」カテゴリのページは、単語を伏字を利用しています。●●●部分(伏字)をクリックすると単語が表示されます。再度クリックすると伏字に戻ります。
- その他重要な単語は赤字で表示しています。
古墳とヤマト政権
古墳の出現とヤマト政権
1 古墳の出現
- 3世紀後半から西日本を中心に、●●●や前方後方墳などが出現
出現期の古墳で最大規模は奈良県●●●古墳 - 内部:長い木管を竪穴式石室に埋葬、副葬品(銅鏡など)
- 性格:各地の首長級に共通の墓制(広域の政治的連合体の形成)。
2 ヤマト政権の成立
- 出現期の古墳 大和地方(奈良)に各地をしのぐ大規模な古墳
- 大和政権:大和地方を中心に近畿中央部の勢力を核とする政治連合
- 4世紀中頃、東北まで古墳が波及 大和政権の支配拡大を示唆